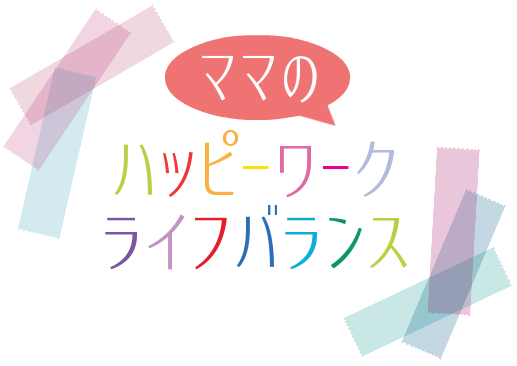結露はどうしてできるのか?その原因は
梅雨の時期、朝起きてカーテンを開けてびっくり!窓がびっしょり・・・ということもあります。
空気中の水蒸気が凝縮して冷やされ、水滴となって窓や床などを濡らしてしまう現象です。
外気温と室内の温度に差があると結露現象が起こります。
冷たい飲み物をグラスに入れて飲んでいると、グラスの周りに水滴がたっぷりつきます。
この状態と結露の状態は同じで、特に冬場は暖房をつけているので外気温との差が大きくなり、結露しやすくなるのです。
結露で健康被害?家計にも影響が?
水分だからそのまま窓についていても乾けば問題ないでしょ?なんて言っているのはまちがいです。
結露で発生するのは確かにただの水ですが、そのままにしてしまうと窓についている汚れや雑菌類、誇りと混ざってカビが発生することもありますし、細菌、ダニの温床となることもあります。
なんだか最近やけに咳が出るという人は、もしかすると結露でできたカビのせいかもしれません。
ぜんそく、アレルギーといった健康被害も起こるのですから、結露対策をしっかり考えておくべきです。
また結露をそのままずっと放置すると、床にいつも水分が付いた状態になり、フローリングが腐り、壁の内部にカビができることもあります。
床、壁の修理で大きな費用がかかることもあるので、結露を甘く見てはいけないのです。
結露防止に換気と十分な乾燥を
結露を防止するためにすぐにでもできる方法が十分な換気を行うこと、また部屋をしっかり乾燥させることです。
窓を拭くときには上から下に向かってふくと、床やカーテンなどを濡らしてしまうことがあります。
結露は下から上に向かってゆっくりと拭いていくと、水滴をうまくふきあげることができるでしょう。
結露取り用のワイパーなども販売されていますので、こうしたグッズを利用するのもおすすめです。
また窓とカーテンの間は意外と風が通らないので、カビがつきやすい箇所です。
結露がついたら窓をきれいに拭き、風を通し湿気を飛ばしましょう。
加湿器の使用とアルコール消毒
喉のために加湿器を利用するのもいいのですが、あまりにも加湿器を使いすぎると湿度が高くなりすぎて結露します。
室内の湿度は40%から50%くらいあれば十分なので、湿度計などをつけて湿度が高くなりすぎないようにするのも重要なポイントです。
もしも結露によってカビが発生してしまった場合、アルコールスプレーが効果的です。
カビがひどいときにはカビとり剤など利用してもいいのですが、パッキンを傷めてしまうこともあるため、素材に合ったもので予防策、対応策を考えます。
サーキュレーターや断熱シートをうまく利用しよう
梅雨時期など雨で窓を開けられないときや、住宅事情で窓を開けるのが無理な方は、サーキュレーター、扇風機などを置いて風を送ります。
窓に向けて風を送ると空気が循環してくれるので結露防止策となるでしょう。
また結露がかなりひどい住宅は断熱シートを貼りつけると効果的です。
外との温度差が少なくなるので省エネにもなりますし、結露も防止してくれます。
シートはホームセンターなどで販売しているので利用してみるといいでしょう。